煎茶道家松ヶ根翼仙先生と行く。六古窯の一つ【丹波焼の郷【立杭】をたずねて
「インターネットや本で得た知識や人に聞いた話をわがもの顔で話す煎茶道家に俺はなりたくない。自分の足で現地にでむいて、つくり手のはなしに耳をかたむけてリアルを感じる。そうすることではじめて、自分の知識に変わる。実際に体験することは本当に大事。」
そう話してくれたのは、京都で活躍する若き煎茶道家松ヶ根翼仙さんです。
私は元京都のホテルスタッフ、まめたこ(Mametako)です。
このサイトは、わたしがおとずれた京都の好きな場所について紹介・発見するサイト。
ですが、京都に限定することなく、日本という大きなくくりで私が出会ったステキなものを紹介するココロミを今回から始めようと思います。
今回、とっておきの旅に連れていってくださったのは、若き煎茶道家松ヶ根翼仙(まつがねよくせん)さん。
時間があれば日本全国を旅して、各地域文化にふれ、感じ、得たものを自身の活動に反映されています。
今回わたしは、松ヶ根翼仙(以後:翼仙先生)に”丹波立杭焼が生まれた立杭”への旅に同行することができました。
ここからは、わたしが覚えている範囲で印象に残ったこと、そして、魅力的だと感じたことを書いていきます。
今回の旅の案内をしてくださった方
松ヶ根翼仙(東叡山翼仙)先生
宮城県大崎市で代々続く歴史ある名家出身。
学生時代に煎茶道の家元に出会い、お稽古を開始。
25歳の時に煎茶道黄檗売茶流教授を拝命。
老舗和菓子屋「とらや」で5年働いた後、現在は日本文化のPR事業を行う傍ら、時間を見つけては全国を旅して、知識を深めている。
大阪市上本町に教室を開き、煎茶道のお稽古・ワークショップを行っている。>>>煎茶道家松ヶ根翼仙さんの旅ブログはこちら
今回の旅の目的地
兵庫県丹波篠山市立杭。
山にかこまれ、川がながれる自然豊かな場所。
旅は突然に。翼仙さんと行く丹波篠山立杭の旅
「源泉100%の温泉に入りたい?」
先日、翼仙先生と大阪の「汐の湯」に行ってきた。
大阪の源泉100%の温泉だ。
温泉の端のほうは茶色に変色し、プツプツと鉄分が付着していた。100%源泉の証らしい。
「むかしのひとは鉄分を多くふくまれる温泉にはいることで、ほうれん草を食べないでも鉄分を摂ることができた」
と、ごくらくな顔をして翼仙先生はつぶやいた。
たしかに、よく貧血をおこすわたしも、今週は一度も貧血をおこさなかった。
「さて、立杭焼、見に行こうか」
旅への誘いはとつぜんである。
どうやら、今回の旅の目的はこれからが本番だとようやく私は気づいた。
翼仙文化教室開催。学べ、【丹波立杭焼】
わたしは、陶器・陶磁器についての知識はなんにもない。
そんなわたしに翼仙先生は、丹波焼きの郷に到着するまでやさしく丹波立杭焼について教えてくださった。
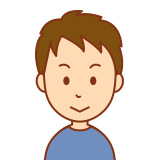
立杭焼ってなに?
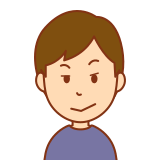
立杭焼は日本六古窯のひとつ【兵庫県丹波篠山市立杭】で作られているうつわ。
立杭焼は、歴史が長く、もともとは農民が自分たちで使うための日曜雑貨として作っていたという。
ただ、日用雑貨として使われていたうつわだけど、うつわの色はまるで自然をそのままうつわにしたような、自然だから魅力的に見える。
立杭焼は・・・ペラペラペラ・・・・ペラペラ・・・。
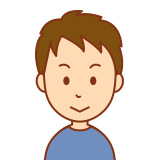
ちょ、・・・え?
もう一回言って?
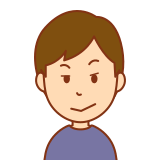
落ち着け!落ち着け!
知識、逃げねーから。
かっこいいっす。
翼仙先生に聞いたはなしをわたしなりにまとめてみた。
余談ですが、「立杭焼」と「丹波焼」の違いわかりますか?
わたしは全然わからなくて・・・、窯元を訪れた時に「立杭焼って丹波焼と何が違うんですか」とたずねましたよ。
答えは、どちらも一緒。丹波焼は「丹波立杭焼」というのが正式名称みたい。
この文章の中では【丹波焼】に統一します。
丹波焼のお話
丹波焼は800年以上前につくられはじめた。
もともとは、農民たちが自分たちが使うために各々の家でつくっていた。
丹波焼は生活雑貨だ。800年経った今も、生活雑貨をつくるカタチは変わっていない。
・・・丹波焼のせつめいを聞いている時に、なんども「ロッコーヨー」という言葉をきいた。
六古窯(ろっこうよう)
日本六古窯とは、平安時代~鎌倉時代にはじまり、現在まで製作がつづいている日本を代表する窯場である。
| 焼物の名前 | 地名 |
| 瀬戸焼 | 愛知県瀬戸市 |
| 常滑焼 | 愛知県常滑市 |
| 越前焼 | 福井県丹生郡越前町 |
| 信楽焼 | 滋賀県甲賀市 |
| 丹波立杭焼 | 兵庫県丹波篠山市 |
| 備前焼 | 岡山県備前市 |
日本のはしっこからはしっこまで、ドラゴンボールのように分かれていると思ったのですが、そんなこともないようね。
丹波焼
話は丹波焼にもどす。
生活雑貨のカタチである丹波焼だが、愛陶家に愛され鑑賞用にもなっている。
生活雑貨として作られた丹波焼がなぜ鑑賞されるほど愛されているのか、その魅力はこうだ。
自然のガラスコーティング
陶磁器を作るときに「釉薬」と呼ばれる薬品をかけて窯で焼くと窯の中でガラス質になり、陶磁器の表面がコーティングされる。
コーティングされたうつわは、水分や汚れからうつわを守り、割れにくく丈夫になる。そしてコーティング部分は様々な色を表現するのである。
穴窯で制作される丹波焼は釉薬を使わずに素焼きだった。
しかし、穴窯で制作される立杭焼はツルっと美しかった!
素焼き・・・釉薬を塗らずに焼いた陶器や磁器。
釉薬(うわぐすり)・・・陶磁器の表面のガラス質。器に水分や汚れがしみ込まないようにする、丈夫になる、そして様々な色を表現する。
自然の釉薬
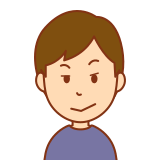
立杭焼を焼く時、穴窯の燃料には松が使われていた。
窯の中では、松が燃え上がり、灰になる。
そして、その灰はうつわにつもる。
窯の熱でやがて溶け出しガラス質に、灰の中の石灰やアルカリ成分と素焼きの中の鉄分が融合し緑色や鳶色を自然発色した。これが自然釉(しぜんゆう)。
そして、この自然釉からヒントを得て、現在は灰釉、人口釉が使用されている。
自然は美しい。
だから自然を、、、自然がうつわに変わったような。
自然がそのままうつわになればそれは美しいに決まってる。
自然をうまく表現しているのが丹波焼。
ふむふむ、なるほど。
自然がうまくうつわに表現できている、しぜんがうつわに宿っているのが丹波焼、ということかなとわたしはそう覚えた。
自然はうつくしい。
なんどもこの言葉が頭の中でリピートした。
・800年変わらず日用雑貨を作り続けている
・自然がうつわに表現されている
丹波焼に革命をもたらした?河井寛次郎とバーナードリーチ
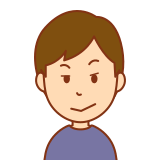
そんな魅力がある丹波焼にはもう一つ特徴がある。
それがスリップウェア。
陶芸家の河井寛次郎とバーナードリーチが丹波焼の里を訪れ、丹波焼に感動し、より良いうつわを作るためのアドバイス、そしてスリップウェアの技法、コップのとってを伝えた。
河井寛次郎とバーナードリーチが丹波焼を評価したことで、丹波焼が全国で人気になった。
ペラペラペラ、、、、、ペラペラ、、、、、
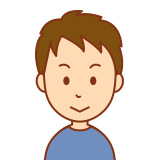
ちょ、、、、え?
スリップ、、なに?
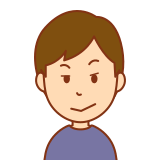
落ち着け!落ち着け!
知識、逃げねーから。
うす。
民藝運動で脚光を浴びた【丹波焼】
「丹波焼は衰退していたけど、陶芸家の河井寛次郎とバーナードリーチに発見されたことで、全国的に人気になった」
と翼仙先生は言っていたので、少しだけ掘り下げて調べてみると、民藝運動が関係あるよう。
民藝運動は、1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です。当時の工芸界は華美な装飾を施した観賞用の作品が主流でした。そんな中、柳たちは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝(民衆的工芸)」と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱え、美は生活の中にあると語りました。そして、各地の風土から生まれ、生活に根ざした民藝には、用に則した「健全な美」が宿っていると、新しい「美の見方」や「美の価値観」を提示したのです。
日本民藝協会のホームページ「民藝とは何か」から引用
以前、鴨川のほとりで軽トラの上に茶室を作って全国まわっている茶道家が、
「日本の美は「用」の中にある。」
と話してくださったのがよみがえる。
民藝活動。こんな活動があったなんて全然知らなかった。
でも、その土地の美しいものを探すってすばらしいな、と思う。
普段なにげなく使ってるもので、わたしたちは気づかなくても実は先人たちの知恵や工夫が活かされていたり、日本人の美意識が含まれているものってたくさんあるんだろうなあ、それを発掘して世に送り出すってすばらしい運動だな。と。
丹波焼は一時は衰退していたが民藝運動を通じて、全国的に人気になったよう。
陶芸家の河井寛次郎、そしてバーナードリーチは丹波焼の里を訪れた時、より良く丹波焼が製作できるようにアドバイスをさずけ、バーナードリーチはスリップウェアという技法を伝えた。
スリップウェア
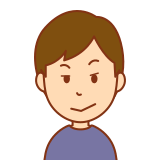
スリップウェアは化粧土をつかって陶器の表面に模様をつける。
スリップウェアはイギリスで見られる技法で、それをバーナードリーチは伝えた。
丹波焼の里【立杭】を歩くとスリップウェアを見つけた。

窯の中で焼きに入れる前にスリップ(化粧土)で模様をつける。
スリップウェアはさわってみるとモコっとなっていた。
スリップウェアとは
スリップウェアは化粧土と泥漿(でいしょう)で装飾した陶器のことです。釉薬は基本的に鉛釉(えんゆう)を施します。
スリップウェアのはじまりは古代メソポタミア文明まで遡るといわれています。古代中国・中東・欧米諸国など世界各国で焼かれた陶器ですが、中でも17世紀のイギリスで作られた作品が広く知られます。
陶磁器~お役立ち情報~スリップウェアとバーナードリーチから引用
なんと。古代メソポタミア文明が起源・・・。
世界中で焼かれたスリップウェアの技法が丹波焼の里までつたわったのか。
丹波焼の里【立杭】は山にかこまれていて、イメージ通りの田舎ってかんじの風景で。
そんなとこで・・・そんなとこでっていう言い方おかしいけど、はるばる出会ったというか。
民藝運動が丹波焼の美しさを世に広めて、スリップウェアと丹波焼を出会わせたんだなあ。
・民藝運動で丹波焼の美しさが全国で評価される
・スリップウェアの技法がつたわる
丹波焼の里を歩く
立杭には現在およそ60の窯元がある。
窯元を訪ねる【窯元路地歩き】もおすすめ。
ぶらぶらと歩きまわるのも楽しい。
路地の写真はない。
ちょっと坂が強くて・・・。
登りがきつくて・・・。
温泉入ったからかな、身体も心もゆるんで写真をほとんど撮りませんでした。

橋にも丹波焼。この装飾はスリップウェア?

路地にはこのように多くの窯元が並ぶ。
バーナードリーチがスリップウェアを伝えた窯元【丹窓窯】
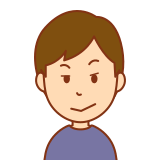
バーナードリーチがスリップウェアを伝えた窯元見たい?
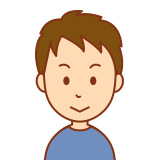
ぜひお願いします!
バーナードリーチが実際にスリップウェアを伝えた窯元が現存する。
そして、現在もスリップウェアが作製されている。





ほんとうにザンネンな話だが、丹窓窯は開いていなかった・・・。
店頭に並んでいるスリップウェアだけしっかりと見せていただいた。
ありがとうございます。
丹波立杭焼がわかる【陶(すえ)の郷】
こちらの施設では、丹波焼の郷にある全ての窯元の作品を見ることが出来る。
丹波焼の郷を一日ですべて見て回ることは不可能。
陶の郷で、窯元の作品を一通り見て、自分が気になった窯元を訪ねると効率的に窯元路地歩きできる。
今回、5,6件の窯元を訪れた際、ほとんどの窯元で【陶の郷】をすすめられた。
・丹波焼の郷のすべての窯元の作品を見ることができる
・陶芸体験も可能(20名以下なら予約の必要なし)
詳細情報は陶の郷ホームページから。
窯元路地歩きのウォーキングマップもダウンロードできる
丹波焼の郷をたずねて
これまでに翼仙さんに紹介していただいて多くの場所を訪れましたが、今回の旅でようやく旅の大切さというか・・・、旅の面白さを理解できたと思います。
旅にでて、その土地のものを食べ、見て、触れる。
その楽しさを少しは感じれたかな、と。
丹波焼。まだまだ分からないことが多いですが、興味を持ちました。
次はどこにいくか楽しみです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
まめたこ(Mametako)




